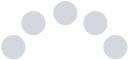ご挨拶
このたび、2025年8月1日付で国際保健医療事業開発学分野の教授に着任いたしました。 2006年に大阪大学医学部医学科を卒業後、臨床研修を経て大阪厚生年金病院(現JCHO 大阪病院)および大阪大学医学部附属病院にて、小児科の専門研修を行いました。その後、大阪大学小児科の大薗先生、北畠先生、小垣先生のご指導のもと博士課程に進み、博士号を取得いたしました。博士課程修了後は、Johns Hopkins 大学公衆衛生大学院において社会疫学者のSurkan教授のご指導を受け、公衆衛生学修士号(MPH)を取得いたしました。
2018年より東京医科歯科大学(現・東京科学大学)にお世話になり、統合教育機構にて秋田先生、木下先生のご指導のもと医師の卒前教育を学びました。2019年からは臨床医学教育開発学分野において田中先生、山脇先生にご指導をいただき、卒後教育に関して学び、研究も進めてまいりました。研究面では、公衆衛生学分野の藤原先生のご指導のもと、社会疫学、国際保健、環境保健など、プラネタリーヘルスの視点から研究を継続してきました。2022年からは公衆衛生学分野に所属し、2024年からはウェルビーイング創成センターのセンター長を務めてまいりました。
小児科医としての臨床経験を通じ、私は環境要因が健康に及ぼす影響の大きさを強く感じてまいりました。その経験を背景に、社会環境や気候変動などの自然環境が人々の健康に与える影響を探る環境医学・プラネタリーヘルスの研究に取り組んでおります。近年では、全国の入院患者データベース(DPC)と気象庁のデータを統合し、川崎病、腸重積、アナフィラキシー、免疫性血小板減少性紫斑病などの入院リスクが暑熱曝露により増加することを明らかにいたしました。
現在は、キルギス共和国における大気汚染の健康影響に関する研究を進めております。同国では大気汚染が深刻な課題とされており、大気汚染に対する介入政策の評価に必要な測定データについても、得られる情報が限られていました。そこで、NASA の衛星データや機械学習、流体力学的シミュレーションを用いて大気汚染濃度を全国的に推定し、その健康影響を明らかにする研究を提案し、JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)に採択されました。本プロジェクトは、日本側は九州大学や聖路加国際大学、キルギス側は大学や省庁からメンバーが参画し、2029 年度まで約5億円規模の研究費のもと実施されています。また、科学的知見を社会実装につなげるため、行動変容を促すコミュニケーション施策にも取り組む予定です。
今後も、高度な統計解析と質的研究の両面から研究や社会実装を進め、社会への還元を目指してまいります。また、次世代を担う人材の育成にも力を注ぎ、教育・研究・社会貢献を通じて大学のさらなる発展に貢献できるように尽力していく所存です。これまでご指導・ご支援を賜りました多くの皆様に心より感謝申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。