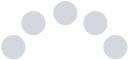
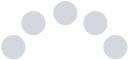
医学研究の成果を臨床で利用するという観点から、診断専門医はその能力を維持するために生涯教育、継続的専門職育成プログラム、医学雑誌、学会活動、インターネットの活用により専門分野の最新研究についていく必要がある。研究結果の解釈とその患者への適用の仕方を認識しておくことが重要であり、研究方法の基本に精通し適切な医療を実践するために専門的視野で広義の教育プログラムを構築していくことも必要である。学術院を効果的に運用し、個々の学部や研究科等の枠を越えた全学的視点に立った、領域横断的な研究活動を実現するための放射線医学的観点を明確化してゆく。また、大学院における教育・研究活動を学部教育へ反映させるとともに、研究成果の更なる向上に向け、企業等との連携強化や外部資金確保対策に積極的に取り組む。北米放射線学会議(RSNA)、米国核医学会(SNMMI)などとの国際協力ネットワークの推進に画像診断・核医学の立場から積極的に取り組み、分野においてもたらされるインパクトや関連実用分野で発展する可能性と言った点についても十分認識した上で研究を推進してゆく。
患者と放射線診断医師双方の期待に応えるために医療の中核となる価値、特に共感、能力、自律について知り自ら示していくことが重要である。放射線診断学には高度の能力が要求されるため、能力を習得するために長期の訓練を要するが、医学的知識の発展を鑑みながら能力の維持も課題となる。また、医療の実践や社会的、政治的環境の変化に対応するため放射線科学的知識や技術のみならず倫理的な知識、技術、能力も同様に維持していく必要がある。学部教育では、自ら課題を見つけ探究する姿勢と様々な問題を解決する能力を備えた人材育成に向けて「問題提起」「技法の修得」「専門との連携」の各科目群を展開し、それを踏まえた専門教育を放射線医学の観点から考案し実施する。大学院教育においては、人類の抱える課題にグローバルな視点から統合的に解決できる人材の育成に向け、専門知識の習得に加え、先端的な課題の研究を複数の教員による研究指導体制のもとで実施し、独創的かつ実践的な研究能力を開発する教育を放射線医学の観点から行う。大学院教育にはこのような観点からの能力維持を継続していくことも重要である。
新しい放射線科専門医制度では、2年間の卒後臨床研修に引き続く日本放射線学会認定研修施設での3年間の総合研修の後(卒後6年目)に放射線科専門医認定試験の受験資格が得られる。合格後、放射線治療あるいは画像診断に分かれてさらに2年間の専門研修の後(卒後8年目)に放射線治療専門医あるいは放射線診断専門医の認定試験受験資格が得られる。