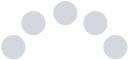
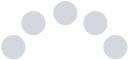
教育として、必要な知識を体系的に伝えながら、学部のうちから「病理」という枠に限らず、疾患の理解と克服に役立つ「医学の最先端」に触れることをencourageし、その助けになりたいと思います。研究面では、疾患とその重症度を見極める診断の基盤を活かし、病理=切片というクラシカルな取り組みを大事にしながら、sequencing, computation, drug discoveryに至るまで、専門分野を超えて患者さんを助け支えるmotivationを共有し、皆で多様なscience and technologyを取り入れ、研究しています。「疾患克服に挑戦する気持ち=助ける病理学」を、スタッフから学生まで、世代を超えて共有します。
同じ診断でも、病勢や治療への応答性が異なるのが、ベッドサイドのreal worldであり、1. Humanized Mouseやpatient-derived xenograftと呼称されるシステムで、生体内での正常・疾患いずれもヒト細胞のdynamicsを知る、2. 個体から、各組織/臓器、細胞、蛋白、遺伝子、代謝物など、複数の階層を繋ぐように網羅的な計測を行い、dataからdiseaseの本質や弱点を見つけ出す、を重要視しています。そのためには、病理だけでなく、多くのコラボレーターと仕事をしており、その方々の元で学ぶことも奨励します。学部生でも大学院生でも医師でも、世界を知る・視る、素晴らしき人に出会う、その繋ぎの役割も担います。また、ビジネスディベロプメントの世界とcollaborateすることで、新しい治療を開発して患者さんの元へと届ける仕組みについて、国内外で取り組んでいます。
詳しくは、分野のホームページ(https://tmdu-comppath.jp)をご覧ください。
1. ヒト血液・免疫・疾患の再現
上記の通り、患者さんそれぞれに疾患の様子も違えば、それを抑えようとする免疫の力も異なります。免疫は、造血幹細胞から作られ、その過程をマウスに再現しながら、どのような遺伝子があれば、強い免疫を作ることができるか、また、白血病が骨で発生して、どのように全身に拡がり、それを阻止できる治療は何かを研究しています。助ける研究には、多様な考えや研究ツールが必要です。
Nature Biotechnology 2007「患者白血病状態を再現。抗がん剤治療に抵抗性を示す白血病細胞の局在を同定」
https://www.nature.com/articles/nbt1350
Nature Reviews Immunology 2007「Humanized Mice: Human biologyの理解から新しい医療へ」
https://www.nature.com/articles/nri2017
2. 白血病再発の理解と治療開発
一旦、化学療法などで減少した白血病細胞が再び増えてくる「再発」を根絶するのが、私たちの大きな目標です。そのために、再発の原因となる細胞を見出し、その中に治療標的を同定して治療を作る。このような取り組みを、多数の患者さんの思いと共に進めてきました。白血病を追い詰めるように連続性を持って研究を進める姿勢と、進めながら、私たちも、変化するテクノロジーを学びつつ、より素晴らしいチームワークを構築する思いを持っています。
Science Translational Medicine 2010「患者白血病の治療標的の同定」
https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.3000349?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
Nature Biotechnology 2010「一部の白血病細胞の細胞周期がG0(静止期)にあることが治療抵抗性・再発の原因に」
https://www.nature.com/articles/nbt.1607
Science Translational Medicine 2013「白血病のリン酸化酵素阻害による治療の提案」
https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.3004387?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
Science Translational Medicine 2017「1細胞解像度でのDNA sequencingと腫瘍特異的変異の同定」
https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.aao1214?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
Nature Cancer 2021「白血病根治を目指す個別最適化治療」
https://www.nature.com/articles/s43018-021-00177-w
3. CRISPR-Casを用いた疾患の治療抵抗性の理解(倉田准教授 病理学会2023 A講演受賞)
倉田准教授は、いち早くCRISPRを学び、国際的なリーダーシップを発揮してきました。腫瘍の治療抵抗性など、長年、解きたいと思ってそう出来なかったことに挑戦しています。
大学院生や若手病理医もCRISPRをそれぞれの研究テーマに上手に含めて、研究のレベルアップを図っています。
Communications Biology 2023 (筆頭著者杉田先生 2024病理学会にて新人賞受賞、倉田准教授指導)
https://www.nature.com/articles/s42003-023-04941-9
Molecular Cancer Research 2022
https://aacrjournals.org/mcr/article/20/11/1646/709850/Proliferation-and-Self-Renewal-Are-Differentially
4. 乳がん、膵内分泌腫瘍、子宮内膜症、脂肪肉腫、悪性中皮腫など、幅広い疾患を対象とする病理学・医学の深化。疾患細胞・間質の関係性の可視化。
血液系の腫瘍だけを研究している訳ではありません。病理スタッフが取り組んできた仕事は、さらなる進化を遂げています。以下、みていただけたら幸いです。
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378111923007576?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023683722003117?via%3Dihub
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pin.13193
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36290460/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35887071/